祈る、ということ。
- kamakurabonz
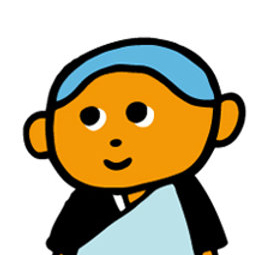
- 2022年2月5日
- 読了時間: 3分
2014/03/31

3月11日、鶴岡八幡宮で「東日本大震災 追悼・復興祈願祭」が執り行われました。鎌倉の神道・仏教・キリスト教、三宗教の宗教者100人余が集まり、それぞれの形で祈りを捧げました。

八幡宮の舞殿で観音経が唱えられ、讃美歌「いつくしみ深き神よ」や「アメイジンググレース」が歌われました。集まった参列者たちは、ともに黙祷し、ともに手をあわせて、お焼香の列に並びました。
最後、インタビューに応えた建長寺の高井宗務総長は、「私たちにできるのは祈ること。毎年開き、鎌倉は被災地のことを決して忘れない、ということを伝えていきたい」と語っておいででした。

後日、アメリカや中国などの在日記者に、鎌倉の復興祈願祭の映像を見せる機会がありました。
参列した数千人の人たちが等しく手を合わせ、お焼香する姿を見て、ある中国人記者が「日本人は誰でも、ああやって祈ることができるのか?」と不思議そうに浄智寺住職の朝比奈さんに尋ねたそうです。それを聞いた朝比奈さんも私たちも、逆にとても驚きました。わたしたちが子どもの頃から当たり前にやっている「祈る」という行為を奪われてしまった人たちがいるという事に気づかされたのです。

「祈ること」。特定の宗教に所属していなくても、日本人なら誰でも「祈り方」を知っています。手を合わせること。時に目をつむること。目の前にはない"何か"に向かって語りかけること。
日本人にとって一番身近な神様は、いわゆる「八百万(やおよろず)の神々」です。空や太陽や、風や雲や、樹や川や海や山や大地や、ありとあらゆるものを畏れ、敬い、感謝する心は、誰に教わるでもなく、私たちの暮らしの中にあります。だから、天気が良ければ「ありがたい」と思い、食事をする時には戴く命に「いただきます」と言い、四季折々の行事を大切にし、遠足の前日にはテルテル坊主をぶら下げるのです。思いやり深く、自然の恵みに感謝して慎ましく生きる日本人ならではのスタイルは、こういった宗教観に根ざすところが大きいでしょう。

でも今は、日々の生活が自然と切り離されて、人間が完全にコントロールする(しようとする)世界で暮らす人が増えて来ています。若い家族は、何か目に見えないものに感謝する心を、我が子に教えることがないかもしれません。それとともに、日本人の美徳である謙虚さや、自然を崇拝する心は、どんどん失われつつあるのではないでしょうか。「祈り方を知らない日本人」になってしまうのでしょうか。
そして・・。私たちが鎌倉に感じる居心地の良さは、もしかしたら、そうした宗教観が今も身近に息づいていることによるのかもしれません。
小さな町の中で、神道も仏教もキリスト教も共存していて、違和感なく町の風景として神社やお寺や教会が溶け込んでいます。
山と海に囲まれた小さな町では、自然を無視して暮らすことはできません。鎌倉の人は、どこか「自然の中で生かされている自分」という意識を共有しているように思います。だから、鎌倉の時間はゆっくりとおだやかに流れ、吹く風はやさしく、人々は笑顔になるのではないでしょうか。

いま、復興祈願祭がベースとなって【鎌倉宗教者会議】という組織が立ち上がり、神道・仏教・キリスト教の三宗教が宗派を越えてつながろうとしています。「豊かな【宗教都市・鎌倉】の実現を目指して・・」というと何か特別なことを目論んでいるかのように聞こえてしまいそうですが、それってシンプルな言い方をすると「祈ることを大切にする町・鎌倉であり続けたい」ということなのかもしれませんね。 この3月は、そんなことを考えさせられた月でした。 ※写真提供:山川龍也、加田務(鎌倉宗教者会議より)




コメント